2025年、生成AIの進化は目覚ましく、多くの企業や組織がその導入を模索しています。しかし、実際に現場でAIがどのように活用され、どのような課題に直面しているのか、具体的な声が聞かれる機会はまだ少ないのが現状です。
そんな中、デジタル庁が内製した生成AIツール「源内(げんない)」の3ヶ月間の運用実績と職員からのフィードバックが公開され、注目を集めています。これは、大規模組織における生成AI導入のリアルな姿を浮き彫りにし、非エンジニアの私たちにとっても多くの示唆を与えてくれます。
デジタル庁「源内」とは何か?その導入背景
デジタル庁が2025年5月から運用を開始した生成AI利用環境「源内」は、職員の業務効率化とAIリテラシー向上を目的として開発されました。政府機関が自らAIツールを内製し、積極的に活用を推進する姿勢は、生成AIが単なる流行ではなく、業務インフラの一部として定着しつつあることを示しています。
単に外部の汎用AIサービスを利用するだけでなく、組織のデータやセキュリティ要件に合わせた内製ツールを開発する動きは、今後の企業における生成AI戦略の方向性を示すものとも言えるでしょう。これは、「生成AI、『使う』から『作る』時代へ。自前構築がもたらす真の競争優位性」でも触れたトレンドと一致します。
職員の声から見えた「使える点」と「物足りない点」
CNET Japanの報道(デジタル庁が内製した生成AIツール「源内」 職員110人が語った“使える点・物足りない点”)によると、「源内」は運用開始から3ヶ月で約1200人の職員のうち950人が利用し、延べ6万5000回以上の利用を記録しました。この高い利用率は、生成AIへの関心と潜在的なニーズの大きさを物語っています。
“使える点”:業務効率化への貢献
- 情報収集・要約: 大量の資料やウェブページから必要な情報を素早く抽出し、要約することで、調査時間を大幅に短縮。
- 文章作成支援: 企画書や報告書の下書き、メール作成など、定型的な文章作成の負担を軽減。
- アイデア出し: 新規施策のブレインストーミングや、課題解決のための多角的な視点提供に活用。
- 議事録作成: 会議の音声データから自動で議事録を生成し、手作業での転記作業を削減。
これらの活用事例は、生成AIが単調な事務作業を代替し、職員がより戦略的・創造的な業務に集中できる環境を創出していることを示しています。
“物足りない点”:残る課題とAIの限界
一方で、職員からは「物足りない点」も挙げられています。
- 情報の正確性(ハルシネーション): AIが生成する情報には誤りが含まれる可能性があり、常にファクトチェックが必要。
- 最新情報への対応: 学習データの限界により、最新のニュースや法改正に対応できない場合がある。
- 専門性の不足: 特定の専門分野における深い知識やニュアンスの理解が難しい。
- プロンプトエンジニアリングの難しさ: 質の高いアウトプットを得るためには、適切な指示(プロンプト)を出すスキルが求められる。
これらの課題は、生成AIを導入するすべての組織が直面するものと言えるでしょう。特に、情報の正確性が求められる政府機関においては、ハルシネーションへの対策は極めて重要です。
組織における生成AI導入の鍵:非エンジニアが学ぶべきこと
デジタル庁の「源内」事例は、生成AIの組織導入を成功させるための重要な示唆を与えています。
1. AIリテラシーの向上と継続的な学習
ツールの導入はあくまで第一歩です。職員一人ひとりがAIの特性(得意なこと、苦手なこと、限界)を理解し、効果的なプロンプトを作成するスキルを習得することが不可欠です。この点については、「生成AI人材育成の最前線」や「なぜ今「生成AI人材育成」が熱いのか?」でも強調している通り、人材育成への投資は不可欠です。
2. ファクトチェックと人間による最終確認
生成AIのアウトプットはあくまで「たたき台」であり、最終的な責任は人間が負うという意識が重要です。特に機密性の高い情報や公開情報においては、徹底したファクトチェック体制を構築する必要があります。これは、「AIの嘘を見破る専門家:「AI出力検証サービス」の登場とその意義」で指摘されているAI出力検証の重要性にも通じます。
3. 倫理的な利用ガイドラインの策定
生成AIの利用には、情報漏洩や著作権、倫理的な問題が常に伴います。「生成AIの「品質」と「倫理」を両立させる方法」でも議論されているように、組織全体で明確なガイドラインを策定し、責任あるAI利用を推進することが求められます。
4. シャドーAIへの対策と公式ツールの魅力向上
デジタル庁のように公式ツールを導入しても、職員が使い慣れた外部のAIツール(ChatGPTなど)を非公式に利用する「シャドーAI」のリスクは残ります。「「公式導入25%」の裏で急増するシャドーAI」で述べたように、公式ツールの利便性やセキュリティを向上させ、職員が自ら選択したくなるような魅力的な環境を提供することが、シャドーAI対策にも繋がります。
まとめ:生成AIは「協業パートナー」としての活用へ
デジタル庁の「源内」事例は、生成AIが組織の業務に深く浸透し、その効果を実感する一方で、技術的な限界や運用上の課題も明確になったことを示しています。生成AIは万能なツールではなく、あくまで人間の業務を「支援」する協業パートナーであるという認識が重要です。
非エンジニアの私たちは、AIの進化に臆することなく、その特性を理解し、賢く使いこなすためのリテラシーと論理的思考力を磨く必要があります。そして、組織としてAIを導入する際には、単にツールを導入するだけでなく、人材育成、運用ルール、倫理ガイドラインの策定といった多角的な視点から戦略を練ることが、真の競争優位性を確立する鍵となるでしょう。
生成AIは私たちの働き方を大きく変える可能性を秘めています。デジタル庁の事例を参考に、あなたの組織でも生成AIとの新しい「協業」の形を模索してみてはいかがでしょうか。


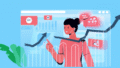
コメント