生成AI活用の主役交代か?事業会社が本腰を入れる時代へ
これまで生成AIの話題といえば、OpenAIやGoogleといったテックジャイアントによるモデル開発競争や、スタートアップによる巨額の資金調達が中心でした。しかし2025年、その潮流は新たな局面を迎えています。主役は、AI開発企業だけではありません。自動車、小売、金融といった、いわゆる「事業会社」が、生成AIの活用に本腰を入れ始めたのです。その象徴的な動きが、自動車大手マツダによる発表でした。
マツダが投じた「400人組織」という一石
2025年9月、マツダが生成AI活用を推進するため、全社横断型の400人規模の新組織を発足させると報じられました。日刊工業新聞社のニュースイッチによると、この組織は「オペレーションのスピードと生産性の劇的な向上」を目的としています。(参考:「生成AI」で生産性劇的に高める…マツダが新組織、全社横断で専任400人 ニュースイッチ by 日刊工業新聞社)
「400人」という規模、そして「全社横断」という体制。これは、もはや一部の先進的な部署が試験的にツールを導入する、といったレベルの話ではありません。研究開発から設計、生産、販売、マーケティングに至るまで、事業のあらゆるプロセスに生成AIを組み込み、会社全体のあり方を根本から変革しようという、経営陣の強い意志の表れと言えるでしょう。
これまでの多くの企業が「まずは使ってみよう」というPoC(概念実証)の段階に留まっていたのに対し、マツダの動きは、生成AIが「実験」から「実装」のフェーズへと完全に移行したことを示しています。これは、日本の製造業、ひいては産業界全体にとって大きな転換点となる可能性があります。
「実験」から「実装」へ:あらゆる業界で加速するAI活用
この動きはマツダに限りません。ITmedia ビジネスオンラインの調査によれば、生成AIを業務で活用している人の割合は、特に「情報通信」や「小売」といった業界で高まっています。(参考:よく使用する生成AIツール 1位「ChatGPT」、2位と3位は? – ITmedia ビジネスオンライン)
例えば、小売業界では、顧客データと生成AIを組み合わせた超パーソナライズドマーケティングが本格化。金融業界では、膨大な市場データの分析やコンプライアンスチェックの自動化が進んでいます。当ブログでも以前、総合商社によるAI企業買収の動きを取り上げましたが、これも自社事業とのシナジーを狙った、事業会社によるAI実装の動きの一環と捉えることができます。
なぜ今、多くの事業会社がAI活用に舵を切り始めたのでしょうか。その背景には、いくつかの要因が考えられます。
- 技術のコモディティ化: GPTシリーズだけでなく、ClaudeやGeminiなど高性能なモデルがAPI経由で安価に利用できるようになり、導入のハードルが劇的に下がりました。もはやChatGPT一強の時代は終わり、用途に応じたツール選択が可能になっています。
- 成功事例の可視化: 先行企業がAI活用によって具体的な成果(コスト削減、売上向上など)を上げた事例が共有されるようになり、投資対効果の予測が立てやすくなりました。
- 「AIデバイド」への危機感: AIを使いこなす企業とそうでない企業の生産性の差が、無視できないレベルまで拡大しつつあります。何もしなければ競争から脱落するという危機感が、経営層を動かしています。
- 社内体制の整備: 多くの企業でトライアルが進む中で、情報漏洩リスクなどを管理するための社内ルール策定が進みました。セキュリティを担保した社内専用環境の構築も現実的な選択肢となり、本格展開への土台が整ったのです。
主戦場は「開発」から「活用」へ
マツダの事例が示すのは、生成AIをめぐる競争の主戦場が、モデルの性能を競う「開発競争」から、いかに自社のビジネスに組み込み、価値を創出するかという「活用競争」へとシフトしている現実です。
重要なのは、もはや「AIを導入するかどうか」ではなく、「AIを前提として、どのように業務プロセスやビジネスモデルを再構築するか」という視点です。これは、非エンジニアのビジネスパーソンにとっても無関係ではありません。現場の業務を最も理解しているのは、現場の皆さん自身です。自社のどの業務にAIを適用すれば最大の効果が得られるのか、そのアイデアこそが、これからの企業の競争力を左右します。
生成AIの活用にはメリットだけでなく注意点もありますが、そのリスクを管理し、組織として推進していく体制を構築した企業が、次の時代の勝者となるでしょう。マツダが鳴らした号砲を、私たちは聞き逃してはなりません。


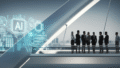
コメント