はじめに
生成AIの進化が加速する中、最新の動向をキャッチアップするためにイベントへの参加を検討している方も多いのではないでしょうか。近年、イベントの開催形式は多様化し、主に「オンライン」と「オフライン(現地開催)」の2つの選択肢があります。それぞれに一長一短があり、どちらが自分にとって最適なのか迷うこともあるでしょう。
そこで今回は、生成AIイベントにおけるオンラインとオフラインのメリット・デメリットを徹底比較し、あなたの目的や状況に合わせた最適な選び方を解説します。この記事を読めば、数多あるイベントの中から、あなたの時間と投資を最大化する選択ができるようになるはずです。
オンラインイベントのメリットとデメリット
まずは、場所を選ばずに参加できるオンラインイベントの特徴から見ていきましょう。
メリット
- 場所と時間の制約がない: 最大のメリットは、インターネット環境さえあれば全国どこからでも参加できる手軽さです。移動時間が不要なため、多忙なビジネスパーソンでも業務の合間を縫って効率的に情報収集ができます。
- コストを抑えられる: 参加費が無料または安価なケースが多く、交通費や宿泊費もかかりません。限られた予算の中で多くの情報を得たい場合に最適です。イベント参加の投資対効果(ROI)を考える上でも重要な要素です。
- アーカイブ視聴が可能: 多くのオンラインイベントでは、後日アーカイブ映像が公開されます。リアルタイムで参加できなくても、自分の都合の良い時間に見返すことができるため、聞き逃した部分の確認や復習に非常に便利です。
- 気軽に質問できる: Q&A機能やチャットを通じて、匿名または気軽に質問を投稿できます。対面では聞きにくい初歩的な質問もしやすいという心理的なメリットがあります。
デメリット
- 偶発的な出会いが少ない: 参加者同士のネットワーキングの機会が限られます。ブレイクアウトルームなどの機能もありますが、オフラインでの雑談から生まれるような自然な交流は期待しにくいでしょう。
- 集中力の維持が難しい: 自宅やオフィスでの参加は、他の業務や通知など、集中を妨げる要因が多くなりがちです。イベントに没入しにくいと感じる人も少なくありません。
- 製品・サービスを直接体験できない: 展示会形式のイベントの場合、実際の製品デモを直接操作したり、質感を確認したりすることができません。画面越しの情報だけでは、導入の判断が難しい場合があります。
- 臨場感や熱気に欠ける: 会場の一体感や登壇者の熱量を肌で感じることが難しく、モチベーション向上に繋がりにくい側面があります。
オフラインイベントのメリットとデメリット
次に、現地に足を運んで参加するオフラインイベントの特徴です。
メリット
- 質の高いネットワーキング: 登壇者や出展企業の担当者、他の参加者と直接顔を合わせて話せるのが最大の魅力です。名刺交換はもちろん、休憩時間や懇親会での何気ない会話から、新たなビジネスチャンスや有益な情報交換が生まれることが多々あります。
- 五感で情報を得られる: 製品のデモンストレーションを目の前で見たり、実際に触れたりすることができます。サービスの細かいニュアンスや担当者の人柄など、オンラインでは得られない非言語的な情報も判断材料になります。
- 高い集中力と没入感: イベント専用の空間に身を置くことで、日常業務から離れて情報収集に集中できます。会場の熱気や参加者の真剣な眼差しは、知的好奇心を刺激し、学習効果を高めてくれるでしょう。
- 深い情報交換が可能: 興味を持ったセッションの後、登壇者に直接質問に行ったり、ブースで担当者とじっくり話し込んだりできます。Webサイトや資料だけではわからない、より踏み込んだ情報を引き出すチャンスです。
デメリット
- コストと時間がかかる: 参加費に加え、会場までの交通費や、遠方の場合は宿泊費も必要になります。また、移動時間を含め、丸一日あるいは数日間を確保する必要があります。
- 物理的な制約: 会場のキャパシティには限りがあり、人気のセッションはすぐに満席になってしまうことがあります。また、体力的な負担も考慮する必要があります。
- 情報の網羅性が低い場合も: 複数の会場で同時にセッションが行われる大規模なカンファレンスでは、聞きたい講演が重なってしまい、どちらかを諦めなければならないケースもあります。
あなたに合うのはどっち?目的別・最適な選び方
結局のところ、オンラインとオフラインのどちらが良いかは、あなたの目的によって異なります。以下に目的別の選び方の指針を示します。
【情報収集フェーズ】最新トレンドを広く浅く知りたい → オンライン
「まずは生成AI業界で今何が起きているのか、全体像を把握したい」という段階であれば、オンラインイベントがおすすめです。コストを抑えながら効率的に複数のセミナーやウェビナーに参加し、次期トレンドを読み解くための基礎知識をインプットするのに適しています。
【課題解決フェーズ】自社の課題に合う具体的なソリューションを探したい → オフライン
「特定の業務課題を解決するためのツールやサービスを探している」という具体的な目的があるなら、オフラインの展示会が最適です。複数のサービスをその場で比較検討し、担当者と直接対話することで、自社に最適なソリューションを見つけやすくなります。
【人脈形成フェーズ】キーパーソンや仲間と繋がりたい → オフライン
業界のキーパーソンと名刺交換をしたい、同じ課題を持つ担当者と情報交換したい、といったネットワーキングが主目的であれば、迷わずオフラインイベントを選びましょう。イベント後の懇親会なども含め、貴重な人脈を築く絶好の機会です。
【スキル習得フェーズ】実践的なスキルを身につけたい → 目的による
ハンズオン形式でツールを操作するなど、実践的なスキルを学びたい場合は、直接質問しやすいオフラインの方が適していることが多いです。しかし、最近ではオンラインでも質の高いワークショップが増えています。自分のレベルや学びたい内容に合わせて、イベントのタイプを吟味することが重要です。
まとめ
生成AIイベントのオンラインとオフラインには、それぞれ異なる価値があります。重要なのは、なぜイベントに参加するのかという目的を自分の中で明確にすることです。
「広く情報を集めたいならオンライン、深く関係を築きたいならオフライン」を基本の考え方としつつ、最近増えている「ハイブリッド開催(オンラインとオフラインの同時開催)」のイベントをうまく活用するのも一つの手です。基調講演はオンラインで視聴し、特に興味のあるセッションや展示ブースには現地で参加するといった、両方のメリットを享受する参加方法も検討してみてはいかがでしょうか。
あなたの目的に合ったイベント形式を選び、得られた知識や人脈を組織の力に変えていくことで、生成AI時代の変化の波を乗りこなしていきましょう。


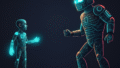
コメント