はじめに:イベントの価値は「受け身」では引き出せない
生成AIに関するイベントやセミナーは、最新動向を掴むための絶好の機会です。しかし、ただセッションを聴講するだけで満足してはいないでしょうか。インプットした知識を自身のビジネスに活かすためには、「受け身」の姿勢から脱却し、能動的に情報を掴みに行く必要があります。その最も強力な武器が「質問力」です。
登壇者や出展企業の担当者は、その分野の最前線で活躍するプロフェッショナルです。彼らとの対話から、Webサイトや資料だけでは得られない「生の情報」や「本音」を引き出すことができれば、イベント参加の価値は何倍にも膨れ上がります。今回は、生成AIイベントでその他大勢から一歩抜け出し、学びを最大化するための「質問の技術」に焦点を当てて解説します。
陥りがちな「もったいない質問」とは?
質疑応答の時間で、誰もが一度は見聞きしたことがあるであろう「もったいない質問」の例をいくつか見てみましょう。これらを避けるだけでも、あなたの印象と得られる回答の質は大きく変わります。
- 漠然とした質問:「生成AIの将来性についてどう思いますか?」→テーマが壮大すぎて、登壇者は一般的な回答しかできません。
- 調べればわかる質問:「御社の〇〇というサービスの料金はいくらですか?」→貴重な対話の機会を、Webサイトで確認できる情報の確認に使うのは非常にもったいないです。
- 一方的な意見表明:「私は〇〇だと思いますが、いかがでしょうか?」→質問ではなく感想になってしまい、議論が深まりません。
- 前提が共有されていない質問:「弊社の基幹システムとの連携についてですが…」→自社の状況を知らない相手には、意図が伝わらず、的を射た回答は期待できません。
これらの質問は、登壇者を困らせてしまうだけでなく、他の参加者にとっても有益な時間とは言えません。では、どうすれば質の高い質問ができるのでしょうか。鍵は「事前準備」にあります。
学びを深める「良い質問」を生む3つの準備
質の高い質問は、その場のひらめきだけで生まれるものではありません。イベントに参加する前の少しの準備が、決定的な差を生み出します。過去の記事「生成AIイベント、参加して後悔しないための『3つの罠』」でも触れたように、目的意識を持つことが重要です。
1. 登壇者とテーマをリサーチし、「仮説」を立てる
まずは、参加するセッションの登壇者の経歴、過去の発信(SNSやブログ、過去の登壇資料など)、そしてテーマについて最低限の情報をインプットしましょう。その上で、「この登壇者は、このテーマについて、おそらく〇〇という見解を持っているだろう」「この技術の最大の課題は△△ではないか」といった自分なりの「仮説」を立てます。この仮説が、質問の出発点となります。
2. 自社の「課題」を具体的に言語化する
次に、「自分(自社)は今、何に困っているのか」を具体的に言語化します。「生成AIを導入したい」という漠然としたレベルではなく、「顧客からの問い合わせ対応の工数を30%削減したいが、どの生成AIツールが最適かわからない」「社内文書の検索精度を上げたいが、情報漏洩リスクをどう管理すれば良いか悩んでいる」といったレベルまで具体化します。課題が具体的であればあるほど、質問もシャープになります。
3. 「背景・課題・質問」のフレームワークで組み立てる
良い質問は、相手に意図がスムーズに伝わる構造を持っています。以下のフレームワークで事前に質問を組み立てておくと、簡潔かつ的確に意図を伝えられます。
- 背景・前提:なぜこの質問をするのか、簡単な背景を共有する。「〇〇業界で営業を担当しており、顧客への提案資料作成に多くの時間を費やしているという背景があります。」
- 課題・試したこと:現在抱えている課題や、すでに取り組んだことを伝える。「現在、ChatGPTを使って資料のドラフトを作成していますが、業界特有の専門用語や最新の市場動向を反映させるのに苦労しています。」
- 聞きたいこと(質問):上記を踏まえ、登壇者の知見を借りたいポイントを明確に尋ねる。「〇〇様がもし同じ立場であれば、このような課題を解決するために、どのようなアプローチやツールを検討されますでしょうか?」
このフレームワークを使うことで、登壇者は質問の意図を正確に理解し、より具体的で実践的なアドバイスを返しやすくなります。
イベント当日に実践したい質問テクニック
準備が整ったら、あとは実践あるのみです。セッションの質疑応答時間や、展示ブース、懇親会など、様々な場面で質問のチャンスは訪れます。
展示ブースでの質問術
製品デモを見ながら「このツールで何ができますか?」と聞くのは初級レベルです。「我々は〇〇という課題を抱えているのですが、このツールはその課題解決にどのように貢献できますか?具体的な導入事例があれば教えてください」と、自社の課題を提示することで、単なる機能説明ではなく、課題解決のパートナーとしての対話が始まります。
懇親会での質問術
懇親会は、登壇者とより近い距離で話せる貴重な機会です。ここでは、セッション内容をさらに深掘りする質問が有効です。「セッションで〇〇とおっしゃっていましたが、その背景にある△△という視点について、もう少し詳しくお伺いしてもよろしいでしょうか?」といった問いかけは、あなたの熱意と理解度の高さを示し、より深い議論へと繋がるでしょう。<こうした場で生まれる人脈が、未来のビジネスチャンスに繋がることも少なくありません。
まとめ:質問力は、イベント参加のROIを最大化するスキル
生成AIイベントへの参加は、時間とコストを伴う投資です。その投資対効果(ROI)を最大化する鍵は、いかに主体的に情報を収集し、自社の文脈に落とし込めるかにかかっています。
今回ご紹介した「質問の技術」は、決して難しいものではありません。少しの事前準備と意識変革で、あなたのイベント体験は劇的に変わるはずです。次のイベントでは、ぜひ「最高の質問者」を目指してみてください。その一つの質問が、あなたのビジネスを次のステージへ進める大きなヒントになるかもしれません。

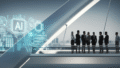

コメント