はじめに:イベントに「答え」を求めていませんか?
生成AIに関するイベントやセミナーが毎日のように開催されています。多くのビジネスパーソンが、最新の知識や成功事例、つまり「答え」を求めて会場に足を運んでいることでしょう。しかし、変化の激しいこの業界において、イベント参加の価値は本当にそこにあるのでしょうか。
結論から言えば、最先端の現場で価値を持つのは、完成された「答え」よりも、次なるイノベーションの種となる良質な「問い」です。本記事では、生成AIイベントの参加目的を「答え探し」から「問い探し」へとシフトさせることの重要性と、そのための具体的な視点について解説します。
なぜ「答え」ではなく「問い」が重要なのか
生成AIの世界では、技術の進化、新しいサービスの登場、法規制の議論などが目まぐるしく進んでいます。半年前の「正解」が、今日では通用しないことも珍しくありません。このような環境下で、イベントで得た断片的な「答え」に固執することは、かえってビジネスの足かせになりかねません。
一方で、良質な「問い」は、陳腐化することがありません。むしろ、ビジネスを前進させるための羅針盤となります。
- 「この技術を業務にどう使えるか?」 → これは「答え」を探す発想です。
- 「この技術の登場によって、これまで解決不可能だった顧客のどんな課題にアプローチできるか?」 → これが、新たな価値創造につながる「問い」を探す発想です。
優れた「問い」を立てる能力こそが、他社との差別化を図り、持続的な競争優位性を築くための鍵となるのです。
イベントで良質な「問い」を見つける3つの視点
では、具体的にどのようにすれば、イベント会場で良質な「問い」を見つけ出すことができるのでしょうか。ここでは3つの視点をご紹介します。
1. セッションの「行間」を読み、未来の課題を探る
多くのセッションでは、成功事例や技術の優位性が語られます。しかし、本当に価値があるのは、その華やかな発表の裏に隠された「語られなかった部分」です。登壇者が触れなかった苦労話、実装段階での壁、そして今後の技術的・倫理的な課題など、その「行間」にこそ、次のビジネスのヒントとなる「問い」が眠っています。
Q&Aセッションは、まさに「問い」を探る絶好の機会です。「そのシステムを社会実装する上での、最大のボトルネックは何ですか?」あるいは「5年後、この技術が社会に浸透した際に起こりうる、予期せぬ問題点は何だとお考えですか?」といった質問は、登壇者から未来の課題を引き出すきっかけになります。こうした質の高い質問力は、周囲の参加者にとっても新たな視点を提供します。
2. 展示ブースでの「非公式な会話」に耳を傾ける
大規模な展示会では、各企業が最新の製品やサービスを展示しています。製品デモやパンフレットから得られる情報は、いわば「公式の答え」です。しかし、私たちが探すべきは、そこに書かれていない市場のリアルな声です。
ブース担当者との何気ない雑談の中に、貴重な「問い」の種が隠されています。「最近、どんな業界からの引き合いが最も多いですか?」「ユーザーから寄せられる最も意外な使い方は何でしたか?」「導入企業が最もつまずくポイントはどこですか?」といった会話を通じて、市場が本当に何を求めているのか、どこにペインポイントを感じているのかという、生々しい課題が見えてきます。これこそが、セッション資料にはない「生の情報」であり、新たな事業開発の起点となる「問い」そのものです。
3. 参加者同士の「共通の悩み」を特定する
イベントの価値は、セッションや展示だけではありません。休憩時間や懇親会でのネットワーキングは、「問い」の宝庫です。様々な業界、異なる職種の参加者と話す中で、「うちの会社でも、まさにそれが課題なんです」といった共感の声が聞かれることがあります。
複数の参加者が同じような悩みや課題を口にしている場合、それは個人的な問題ではなく、業界全体が直面している「共通の問い」である可能性が高いでしょう。例えば、「生成AIの費用対効果をどう測定すればいいのか」「プロンプトの属人化をどう防ぐか」といった悩みは、多くの企業が抱える普遍的な課題です。こうした共通課題を特定できれば、それを解決するソリューションは大きなビジネスチャンスに繋がります。人脈作りが新たなビジネスチャンスを拓くとは、まさにこのことを指すのです。
まとめ:持ち帰るべきは「問い」のリスト
生成AIイベントへの参加は、受動的に知識を受け取るだけの場ではありません。自ら積極的に課題を発見し、未来を洞察するための「問い」を探求する場です。
イベントが終わったとき、あなたの手元に残るべきなのは、完璧にまとめられた議事録や大量の資料ではなく、「自社に持ち帰って検証すべき問いのリスト」です。そのリストこそが、単なる情報収集を越え、あなたのビジネスを次のステージへと押し上げる、最も価値ある成果物となるでしょう。

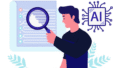
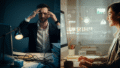
コメント