生成AIの進化は目覚ましく、多くの企業がその可能性に注目し、導入を検討しています。しかし、実際に「導入」のフェーズから「活用」のフェーズへ移行し、ビジネス価値を最大化するには、非エンジニアの担当者にとって多くの課題が存在します。このような背景から、実践的な知見を共有し、企業における生成AI活用を加速させるための動きが活発化しています。
生成AI推進担当者会議の重要性
最近、株式会社グラファーが主催した「第1回 生成AI推進担当者会議」には、約30名もの企業担当者が参加しました。これは、生成AIの導入が進む中で、各社が直面する共通の課題や成功事例を共有し、実践的なノウハウを学ぶ場として非常に有意義なものです。企業の生成AI活用を加速するグラファー主催「第1回 生成AI推進担当者会議」に約30名が参加というニュースリリースからも、企業が具体的な推進戦略を求めていることが伺えます。
この会議のような場がなぜ重要なのでしょうか。それは、生成AIの導入が単なるツール導入に留まらず、組織全体の変革を伴うからです。非エンジニアの担当者が、技術的な側面だけでなく、ビジネスへの適用、リスク管理、組織文化への浸透といった多角的な視点から生成AIを推進するためには、他社の経験から学ぶことが不可欠となります。
会議で共有された実践的知見と非エンジニアのための戦略
会議では、参加企業が生成AIの導入・活用における具体的な課題や成功事例を共有し、活発なディスカッションが行われたとのことです。ここでは、非エンジニアの視点から特に重要となるポイントと、それに対する具体的な戦略について掘り下げていきます。
1. 実現可能性の高いユースケースの選定
生成AI導入の初期段階で最も重要なのは、ビジネス価値が高く、かつ技術的に実現可能性の高いユースケースを選定することです。ガートナーが指摘する「しくじり10選」にもあるように、生成AIだけで全ての問題を解決しようとすることや、実現可能性の低いユースケースに初期投資を集中することは失敗の原因となります。【ガートナー解説】生成AI活用「しくじり10選」、回避のための「投資と教育」とはで詳細が述べられているように、業界特有の分析を行い、自社にとって最適なユースケースを見極めることが成功への第一歩です。
このブログでも、生成AI導入で失敗しない!非エンジニアのためのビジネス価値最大化ユースケース選定術や生成AI導入の落とし穴:ガートナーが警告する「しくじり10選」と非エンジニアのための回避戦略で、このテーマの重要性を繰り返しお伝えしています。
2. 導入で終わらせない「活用」へのコミットメント
生成AIの導入はスタートラインに過ぎません。真の価値は、導入後にいかに現場で「活用」を定着させ、業務効率化や新たな価値創出につなげるかにあります。SIGNATEが提供する「生成AI×業務効率化コース」は、まさに生成AIを“導入”で終わらせないための実践的な教育プログラムであり、多くの企業が注目しています。SIGNATE、生成AIを“導入”で終わらせない「生成AI×業務効率化コース」を提供開始は、この課題に対する具体的な解決策を示しています。
この点については、生成AIを「導入」で終わらせない:SIGNATEの業務効率化コース活用術でも詳しく解説しています。組織内の「活用の溝」を埋めるための戦略は、非エンジニアの推進担当者にとって特に重要です。
3. 社員の発想力と顧客体験(CX)の向上
生成AIは、単なる作業効率化ツールに留まらず、社員の発想力を刺激し、新たな顧客体験(CX)を創出する可能性を秘めています。生成AIで「社員の発想力」を磨け CX向上につながる3つの活用術にあるように、AIをクリエイティブなパートナーとして活用することで、企画立案やコンテンツ制作のプロセスが劇的に変化します。これにより、従業員のエンゲージメント向上はもちろん、顧客への提供価値も高まります。
関連して、生成AIで社員の発想力を磨き、顧客体験(CX)を革新する新常識もぜひご参照ください。
4. 安全かつ倫理的な利用の徹底
生成AIの活用においては、その利便性と同時に潜在的なリスクにも目を向ける必要があります。AIが生成する情報の誤り(ハルシネーション)や、個人情報・機密情報の漏洩リスクなど、安全な利用のためのガイドライン策定と従業員への教育は不可欠です。便利な生成AIだけど…安全に使うための注意事項。AIの嘘を見抜き、個人情報を守るために意識すべきことは?といった記事が示すように、非エンジニアであってもAIの特性を理解し、適切な利用を心がけることが重要です。
この課題については、生成AIを安全に使う新常識:AIの誤情報と個人情報漏洩を防ぐ実践ガイドや、生成AIの信頼性を高める:品質と倫理を両立させる戦略で詳しく解説しています。
生成AI推進担当者に求められる役割と今後の展望
グラファーの「生成AI推進担当者会議」のような取り組みは、企業が生成AIを単なる一過性のトレンドとしてではなく、長期的なビジネス戦略の柱として捉え、組織的に導入・活用していく上で不可欠なものです。非エンジニアの生成AI推進担当者は、技術とビジネスの橋渡し役として、以下のような役割が求められます。
- **情報収集と学習:** 最新の生成AI技術やサービス動向を常に把握し、自社に適用できる可能性を探る。
- **社内啓蒙と教育:** 従業員への生成AIリテラシー教育を推進し、活用文化を醸成する。
- **ユースケースの発見と推進:** 現場の課題を深く理解し、生成AIで解決できる具体的なユースケースを発掘・実現する。
- **リスク管理とガバナンス:** 安全で倫理的なAI利用のためのルール作りと運用をリードする。
これらの役割を果たすことで、企業は「伴走型支援」を受けながら、生成AIを真の競争力に変えることができるでしょう。
まとめ
生成AIの企業導入は、まだ始まったばかりのフェーズであり、多くの企業が試行錯誤を続けています。しかし、「生成AI推進担当者会議」のような実践的な情報共有の場を通じて、成功への道筋がより明確になってきています。非エンジニアの担当者こそが、これらの知見を積極的に吸収し、自社の生成AI活用をリードしていくことが、これからのビジネス成長の鍵となります。
本ブログでは、引き続き生成AIの最新動向や非エンジニア向けの活用術について発信していきますので、ぜひご期待ください。

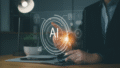
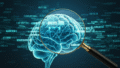
コメント