生成AIの進化は目覚ましく、多くの企業や個人がその可能性に期待を寄せています。しかし、いざ導入を検討しても「具体的にどう使えばいいのか分からない」という壁に直面する非エンジニアの方も少なくありません。2025年現在、この「使い方がわからない」という課題は、生成AIの普及を阻む大きな要因の一つとなっています。
現状の課題:活用したいが「使い方がわからない」
アルサーガパートナーズ株式会社が2025年9月に発表した「生成AI活用実態調査|製造業編」によると、生成AI活用者の約9割が業務効率の向上を実感している一方で、未活用層の約半数が「使い方がわからない」ことを理由に導入を見送っていることが明らかになりました。これは、生成AIの潜在的な価値は広く認識されているものの、具体的な活用方法や導入プロセスに関する情報が不足している現状を示しています。
特に製造業では、品質管理、設計支援、ドキュメント作成など、生成AIが貢献できる領域は多岐にわたります。しかし、現場の担当者が自社の業務にどうAIを組み込むか、その第一歩が踏み出せずにいるケースが少なくありません。
「使い方がわからない」を乗り越える実践的アプローチ
この「使い方がわからない」という課題を乗り越え、生成AIを非エンジニアでも実用レベルで活用していくためには、具体的なユースケースの学習と実践的なスキルの習得が不可欠です。
1. 具体的なユースケースの共有と学習
生成AIの活用事例は日々増え続けており、それらを学ぶことが第一歩です。例えば、一般社団法人生成AI活用普及協会(GUGA)は1,000件超の国内事例を無料で閲覧できるデータベースを公開しています。また、Google Cloudも生成AI導入の「設計図」101選を公開し、実用化を促進しています。
当ブログでも、これらの情報源を活用した記事を公開しています。具体的なヒントを得るために、以下の記事もぜひ参考にしてください。
2. 特定分野での深掘り事例:研究・医療分野での活用
特定の分野に特化した活用事例を知ることは、自社の業務への応用を考える上で非常に有効です。例えば、日経BP Medicalが2025年9月に報じた記事には、研究・医療分野における生成AIの具体的な活用例が紹介されています。
-
海外学会発表の質疑応答支援
海外学会での発表は、言語の壁や即興での質疑応答が大きなハードルとなります。生成AIを活用すれば、リアルタイムでの翻訳支援や、想定される質問への回答案生成、さらには発表内容の要約作成など、多角的にサポートを受けることが可能です。これにより、非英語圏の研究者でも自信を持って国際舞台で活躍できるようになります。
参考:海外学会発表の質疑応答も、生成AIがあれば怖くない! -
文献検索・要約と知識アップデート
研究者にとって、膨大な文献の中から必要な情報を探し出し、内容を把握することは時間と労力を要する作業です。生成AIは、文献の高速検索、要約作成はもちろんのこと、関連する最新の論文や研究動向を自動で提案し、知識のアップデートを効率化します。さらに、新しい研究アイデアの壁打ち相手としても機能し、発想の質を高める助けとなります。
参考:文献検索や要約だけじゃない! 生成AIで手軽に知識をアップデート
これらの事例は、単なる文章生成に留まらない、生成AIの高度な情報処理能力と問題解決能力を示しています。非エンジニアでも、これらのツールを使いこなすことで、専門性の高い業務を効率化し、新たな価値を生み出すことが可能になるのです。
3. 専門的な学習機会の活用
「使い方がわからない」という課題を根本的に解決するには、体系的な学習が有効です。Ragateが提供する「最先端のAI×DXを1日で速習する 生成AI×Dify×Amazon Bedrock 実践講座」のように、短期集中で生成AIの導入戦略からシステム構築・運用までを学ぶ講座は、非エンジニアが内製化を進める上で非常に役立ちます。また、SIGNATEが提供する「生成AI×業務効率化コース」のように、導入後の具体的な業務改善に焦点を当てたコースも、実践的なスキルを身につける上で有効です。
当ブログの関連記事もご参照ください。
4. プロンプトエンジニアリングの習得
生成AIを使いこなす上で最も重要なスキルの一つが、適切な指示(プロンプト)を与える能力、すなわちプロンプトエンジニアリングです。AIの性能を最大限に引き出し、意図した通りの出力を得るためには、プロンプトの設計が鍵となります。
当ブログでは、プロンプトエンジニアリングに関する詳細な記事も提供しています。ぜひ参考にしてください。
非エンジニアが生成AIを「戦力化」するために
生成AIは、単なるツールではなく、私たちの業務や働き方そのものを変革する可能性を秘めた「戦略的パートナー」となり得ます。製造業における業務効率化から、研究・医療分野における高度な情報処理まで、その活用範囲は広がる一方です。
「使い方がわからない」という壁は、決して乗り越えられないものではありません。具体的な事例を学び、実践的なスキルを身につけ、適切な学習機会を活用することで、非エンジニアの方でも生成AIを強力な武器に変えることができます。
生成AIの導入を成功させ、ビジネス価値を最大化するための戦略については、以下の記事も参考になるでしょう。
このブログでは、引き続き生成AIの最新動向や具体的な活用事例、非エンジニア向けのヒントを発信していきます。生成AIを「使いこなす」ための知識とスキルを身につけ、あなたのビジネスやキャリアを次のレベルへと引き上げましょう。


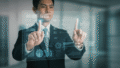
コメント