2025年、生成AIはもはや単なるバズワードではなく、ビジネスのあり方を根本から変革する強力なツールとして認識されています。しかし、その急速な技術進化と多様なサービスが登場する中で、「自社にどう活用すれば良いのか?」「具体的な用途は?」「技術的な課題は何か?」といった疑問を抱え、導入と活用の間に「溝」を感じている企業は少なくありません。
こうした企業の課題意識に応えるべく、2025年9月18日にはインプレス主催のセミナー「生成AI Day 2025」が開催されます(インプレス、セミナー「生成AI Day 2025」を9月18日に紀尾井カンファレンスで開催)。本記事では、このセミナーの開催意図から、企業が生成AI導入で直面するリアルな課題と、非エンジニアでも理解できる実践的な解決策について深掘りします。
生成AI導入における「活用の溝」とは?
デロイトトーマツグループが今年7月に実施した調査でも、多くの企業が生成AIの活用に意欲的である一方で、具体的な導入と活用の間でギャップがあることが示されています(企業における生成AIのリアルとは?導入と活用の間に溝も【最新調査】)。この「活用の溝」は、主に以下の3つの疑問に集約されます。
- 自社にどう活用すれば良いのか?:生成AIのポテンシャルは理解しているものの、具体的なビジネス課題と結びつけられない。
- 具体的な用途は?:どのような業務に適用できるのか、成功事例が見えにくい。
- 技術的な課題は何か?:導入後の運用やセキュリティ、データ連携に関する不安。
これらの疑問を解消し、生成AIを真の「戦力」とするためには、漠然とした期待感だけでなく、現実的な視点と戦略的なアプローチが不可欠です。
「自社にどう活用すれば良いのか?」:ユースケースの特定とスモールスタート
生成AI導入の第一歩は、自社のビジネス課題を明確にし、そこに生成AIがどのような価値を提供できるかを具体的に検討することです。例えば、定型業務の自動化、顧客対応の効率化、コンテンツ作成の支援などが考えられます。
いきなり大規模なシステム導入を目指すのではなく、まずは特定の部署や業務でスモールスタートを切ることが成功への鍵となります。例えば、社内FAQの自動応答システムや、会議議事録の要約ツールなど、比較的小規模なプロジェクトから始め、そこで得られた知見や効果を基に、徐々に適用範囲を広げていく戦略が有効です。このアプローチは、初期投資のリスクを抑えつつ、生成AIの具体的な効果を実感する上で非常に重要です。
関連記事:企業における生成AIの「活用の溝」を埋める:非エンジニアが知るべき実践戦略
「具体的な用途は?」:非エンジニアが知るべき業務変革事例
生成AIの用途は多岐にわたりますが、非エンジニアの方々が特に注目すべきは、日々の業務を効率化し、生産性を向上させる具体的な事例です。
- ドキュメント作成・要約:報告書、メール、議事録などの下書き作成や、長文の資料から要点を抽出。
- データ分析支援:ExcelのCOPILOT関数のように、自然言語で指示するだけでデータ集計や分析をサポート(ExcelのCOPILOT関数、何がすごい?データ集計・分析の常識が変わる)。
- 顧客対応:チャットボットによる顧客からの問い合わせ対応や、FAQの自動生成。
- マーケティング・コンテンツ制作:キャッチコピー、ブログ記事、SNS投稿のアイデア生成や初稿作成。
- プログラミング支援:コードの自動生成やバグの特定。非エンジニアでもWebアプリ開発が可能になるケースも増えています(生成AIによるWebアプリ開発:非エンジニアがビジネスアイデアを形にする新時代)。
これらの用途は、既存の業務プロセスに生成AIを組み込むことで、劇的な効率化と品質向上をもたらします。重要なのは、AIに任せるべきタスクと人間が判断すべきタスクを適切に区別することです。
「技術的な課題は?」:非エンジニアが押さえるべきポイント
生成AIの導入には、いくつかの技術的な課題も伴います。これらを理解し、適切な対策を講じることが成功には不可欠です。
1. データ準備と精度向上
生成AIの出力精度は、入力データとプロンプトの質に大きく左右されます。社内データに基づいた回答を求める場合は、RAG(Retrieval Augmented Generation)などの技術で外部知識を取り込んだり、特定の業務に特化したファインチューニングを行うことで、回答精度を高めることができます(行政DXの要:生成AIの信頼性を高めるRAGとファインチューニング戦略)。また、プロンプトの記述方法も非常に重要であり、「記号と変数」を活用した構造化プロンプトは、より的確な出力を引き出すための強力な手法です(生成AIの出力精度を劇的に高める「記号と変数」プロンプト活用術)。
2. セキュリティとガバナンス
機密情報や個人情報の取り扱いには細心の注意が必要です。NTTデータグループが2025年度中に拡充を予定しているような、プライベート環境での生成AI活用支援サービスは、セキュリティリスクを低減し、企業独自のデータガバナンスを確立する上で有効な選択肢となります(プライベート環境での生成AI活用を支援するサービスを2025年度中に拡充)。
関連記事:生成AI導入の落とし穴:見過ごしがちなセキュリティ脅威と対策
3. GPUリソースの確保とインフラ
高性能な生成AIモデルを動かすには、GPUといった計算資源が不可欠です。自社で大規模なインフラを構築するのが難しい場合でも、GPUクラウドサービスを活用することで、必要なリソースを柔軟に調達できます(生成AI開発を加速する、GPUクラウドサービスという選択肢)。また、ABEJA PlatformのようなPaaS型AI基盤は、非エンジニアでも生成AIモデルの開発・運用を容易にする選択肢として注目されています(生成AI開発企業おすすめ10社と依頼時のポイントを解説)。
関連記事:ABEJA Platformが拓く生成AI開発の未来:非エンジニアも活用できるPaaS型AI基盤の力
生成AIを「戦力化」するための3つの鍵
LayerX CTOの松本勇気氏の著書『生成AI「戦力化」の教科書』が示すように、生成AIを単なるツールで終わらせず、真の戦力とするためには、非エンジニアも以下の3つの鍵を意識することが重要です(LayerX CTO松本勇気著、『生成AI「戦力化」の教科書』を10月24日に発売)。
1. 明確な目的設定とビジネス課題への紐付け
「何のために生成AIを導入するのか」という目的を明確にすることが最も重要です。技術ありきではなく、自社の具体的なビジネス課題や目標に生成AIをどう貢献させるかを考え抜くことで、PoC(概念実証)止まりにならず、実益に繋がる導入が可能になります。
2. 適切なパートナー選びと内製化のバランス
生成AIの開発・導入には専門知識が求められます。初期段階では外部の専門企業やコンサルタントの支援を受けることが有効ですが、将来的には自社内でのAIリテラシー向上と内製化を目指すことが、持続的な競争優位性を築く上で不可欠です。外部パートナーとの協業を通じて、知識やノウハウを社内に蓄積していく視点を持つべきでしょう。
3. 継続的な学習と組織文化の醸成
生成AIの技術は日進月歩で進化しています。最新の動向を常にキャッチアップし、社内での学習機会を設けることで、組織全体のAIリテラシーを高めることが重要です。日経BPが提供開始した生成AI活用事例と最新動向を伝える新サービス(専門記者による解説とAI活用事例を毎週配信、日経BPが新サービス開始)なども、情報収集の一助となるでしょう。
関連記事:生成AI人材育成の最前線:DMM CAMPと実践的「生成AI道場」が拓く未来
まとめ
「生成AI Day 2025」のようなセミナーは、企業が生成AI導入の「活用の溝」を埋め、具体的なアクションへと繋げるための貴重な機会となります。非エンジニアの方々も、生成AIの技術的な側面だけでなく、それが自社のビジネスにどのような変革をもたらすのか、そしてその実現のためにどのような課題をクリアすべきかを理解することが重要です。
生成AIは、正しく戦略的に導入・活用することで、企業の競争力を飛躍的に高める可能性を秘めています。この機会に、自社の生成AI戦略を再考し、次なるビジネス成長のフェーズへと進むための一歩を踏み出しましょう。

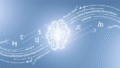
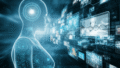
コメント