はじめに:情報過多の時代だからこそ、イベントの「生の情報」が価値を持つ
生成AIの進化スピードは凄まじく、毎日新しいニュースやサービスが生まれています。WebメディアやSNSを追いかけるだけでも一苦労ですが、特に非エンジニアの方にとっては、「技術的な解説を読んでも、結局どうビジネスに活かせるのか分からない」という悩みも多いのではないでしょうか。
断片的な情報を集めるだけでは、体系的な知識や具体的な活用イメージはなかなか掴めません。そんな情報過多の時代だからこそ、価値を増しているのが「生成AIイベント」です。専門家による講演や企業の導入事例、最新技術のデモなどを通じて、体系的かつ実践的な「生の情報」に触れることができます。
今回は、特定のイベント紹介ではなく、なぜ今、特に非エンジニアが生成AIイベントに参加すべきなのか、そして参加効果を最大化するための「3つの視点」について深掘りします。過去の記事『なぜ今、生成AIイベントに参加すべきか?得られる5つのメリット』では参加するメリット全般を解説しましたが、本記事ではより「非エンジニアのビジネス活用」に焦点を当てて解説していきます。
視点1:「技術スペック」ではなく「課題解決のストーリー」を収集する
イベントのセッションでは、多くの企業が自社の生成AI活用事例を発表します。ここで非エンジニアが注目すべきは、使われている技術の細かいスペックやアーキテクチャではありません。むしろ、「どのようなビジネス課題を」「どのような発想とプロセスで」「生成AIを使って解決したのか」という一連のストーリーです。
例えば、「問い合わせ対応の工数を30%削減した」という事例があったとします。ここで重要なのは、単に「ChatGPTを導入した」という事実ではありません。
- Before(課題):なぜ問い合わせ対応が負担になっていたのか?(人員不足、属人化、対応品質のばらつきなど)
- Process(試行錯誤):導入にあたり、どのような壁があったのか?(情報漏洩リスクへの対策、期待した回答精度が出ない、社員の抵抗など)
- After(成果):工数削減以外に、どのような副次的効果があったのか?(顧客満足度の向上、オペレーターのストレス軽減、新たなインサイトの発見など)
こうした「ストーリー」を収集し、自社の状況と照らし合わせることで、単なる知識ではなく、実践的な打ち手としてのヒントが得られます。成功事例だけでなく、失敗談や苦労話こそ、自社で導入を進める上での貴重な道標となるでしょう。こうしたリアルな情報は、Web上の美化された記事からは得にくい、イベントならではの価値と言えます。自社の生成AI活用の実態と照らし合わせ、具体的なアクションプランを練るための材料を集めましょう。
視点2:「誰と繋がるか」を明確にしてネットワーキングに臨む
イベントのもう一つの大きな価値は、普段は接点のない多様な人々と繋がれるネットワーキングの機会です。しかし、ただやみくもに名刺交換を繰り返すだけでは、あまり意味がありません。非エンジニアだからこそ、明確な目的を持って臨むべきです。
例えば、以下のような目的を設定することが考えられます。
- 情報交換相手を探す:自社と同じ業界・同じ課題を持つ企業の担当者と繋がり、クローズドな情報交換を行う。
- ツール・サービスの選定:導入を検討しているサービスの提供企業担当者から、直接デモを見せてもらい、Webサイトだけでは分からない詳細な質問をぶつける。
- 協業パートナーを探す:自社の弱みを補完してくれる技術やサービスを持つ企業を探し、協業の可能性を探る。
講演の合間の休憩時間や懇親会は、絶好の機会です。「〇〇という課題があるのですが、御社ではどうされていますか?」といった具体的な問いから始めることで、表層的な挨拶だけでなく、深い議論に発展する可能性が高まります。イベントで得た知識や人脈をどうビジネスに繋げるかは、イベント後の社内展開にも大きく影響します。目的意識を持ったネットワーキングを心がけましょう。
視点3:未来のトレンドを「知識」ではなく「体感」として持ち帰る
大規模な展示会(EXPO)などでは、多くの企業がブースを出展し、最新技術のデモンストレーションを行っています。セッションで語られる事例が「現在」の活用法だとすれば、展示ブースは「未来」の可能性に触れる場所です。
文章や動画で見るのと、実際に自分の目でデモを見て、担当者に質問しながら触れてみるのとでは、得られる理解度やインパクトが全く異なります。AIエージェントが自律的にタスクをこなす様子や、マルチモーダルAIが画像や音声を即座に認識・処理する様子などを目の当たりにすることで、「3年後、5年後のビジネスはこう変わるかもしれない」という未来像を具体的にイメージできるようになります。
この「体感」こそが、自社の中長期的な戦略を考える上での重要なインプットとなります。次期トレンドを読み解く視点を持ちながらブースを回ることで、単なる情報収集に終わらない、未来への洞察を得ることができるでしょう。
まとめ:目的意識がイベント参加の成果を左右する
生成AIイベントは、最新情報を効率的にインプットし、貴重な人脈を築くための絶好の機会です。特に、日々の業務で直接AI技術に触れる機会の少ない非エンジニアの方々にとって、その価値は計り知れません。
しかし、ただ参加するだけでは情報のシャワーを浴びて終わってしまいます。今回ご紹介した「課題解決のストーリー」「目的あるネットワーキング」「未来の体感」という3つの視点を意識することで、イベントで得たものを明日からのビジネスに活かす具体的な武器に変えることができるはずです。
今後イベントを探す際には、良質なイベントを見抜くポイントも参考にしながら、ぜひ積極的に参加を検討してみてください。
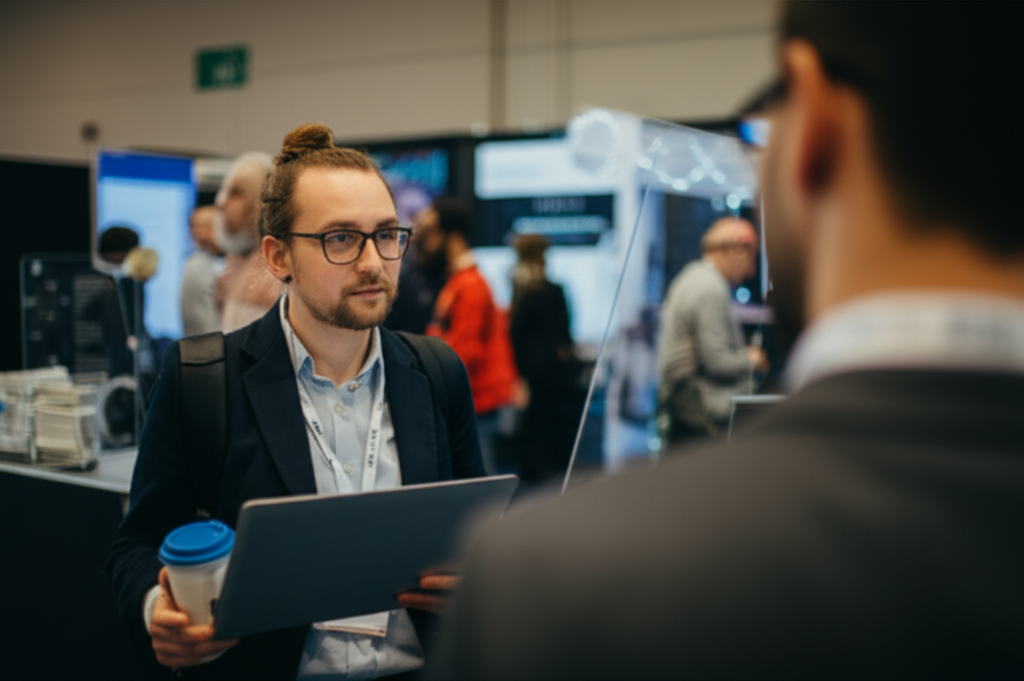


コメント