はじめに:情報の洪水と「参加疲れ」
生成AIに関するイベントやセミナーが、毎日のように開催されています。最先端の知識を求めて参加するものの、あまりの情報の多さに圧倒されたり、どの情報が本当に自社にとって有益なのか見極めきれずに「参加疲れ」を感じてしまったりする方も少なくないでしょう。
最新技術の発表や華やかな成功事例に目を奪われがちですが、イベントの本当の価値は、そうした「熱狂」の少し先にあるのかもしれません。本記事では、生成AIイベントの表層的な情報に惑わされず、自社のビジネスに直結する本質的な価値を見つけ出すための3つの視点について掘り下げます。
視点1:流行りの技術(What)から、実践的な導入法(How)へ
多くのセッションでは、新しく登場した生成AIモデルが「何(What)をできるのか」が語られます。テキスト生成、画像生成、動画生成など、その驚くべき能力に感心するのは当然です。しかし、ビジネスパーソンが本当に知りたいのは、その技術を「どのように(How)自社の業務に組み込むか」ではないでしょうか。
価値ある情報を得るためには、以下の点を意識してみましょう。
- 質疑応答での「深い質問」に耳を傾ける:「導入時の最大の障壁は?」「費用対効果はどのように測定したか?」といった、実践者ならではの質問と回答には、Webサイトには載っていないリアルな情報が詰まっています。
- ネットワーキングで「導入の泥臭さ」を尋ねる:登壇者や他の参加者と話す機会があれば、「社内の説得はどう進めたか」「どのツールを比較検討したか」など、導入プロセスの具体的な話を聞き出してみましょう。
例えば、情報漏洩リスクを懸念してAI導入に踏み切れない企業は少なくありません。そうした課題に対し、「社内専用ChatGPT」構築のススメ:情報漏洩リスクを回避し、AI活用を組織に根付せる方法のような具体的な解決策について、実際に取り組んだ人の生の声を聞けるのはイベントならではの価値です。
視点2:「成功事例」の裏にある「生々しい課題」にこそ価値がある
イベントで発表される事例は、美しく編集された「成功物語」であることがほとんどです。もちろん、それらから学ぶことも多いですが、同じくらい価値があるのが、その裏に隠された「失敗」や「課題」です。
自分たちと同じような課題を抱えている企業を見つけることは、大きな収穫となります。
- 共感できる課題の発見:「プロンプトが属人化して困っている」「現場の従業員がなかなか使ってくれない」といった悩みを共有できる相手を見つけることで、孤独感が和らぎ、解決へのモチベーションが湧いてきます。
- 課題解決の協創:同じ課題を持つ企業同士で情報交換をしたり、ときには共同でソリューション開発を検討したりと、新たなビジネスチャンスに繋がる可能性も秘めています。
多くの企業が直面する生成AI活用の次なる壁:「プロンプトの属人化」を防ぐ組織的アプローチといったテーマについて、他社がどのように取り組んでいるかを知ることは、自社の戦略を練る上で非常に重要なインプットとなります。
視点3:スピーカーだけでなく、「隣の参加者」が未来のパートナー
イベントの主役は登壇者ですが、宝の山は客席にも広がっています。あなたと同じように課題意識を持ち、情報を求めて参加している人々こそ、最も価値のある情報源であり、未来のビジネスパートナーになり得る存在です。
休憩時間や懇親会は、積極的に他の参加者と交流する絶好の機会です。一方的に自分の話をするのではなく、「どんな課題感で参加されたのですか?」「今日のセッションで何かヒントはありましたか?」と相手の話に耳を傾けることで、思わぬ発見があるはずです。
プレゼンテーション資料にはまとめられていない、こうしたセッション資料にはない「生の情報」にこそ、イベント参加の真価が隠されています。
まとめ:イベントを「投資」に変えるために
生成AIイベントへの参加は、時間もコストもかかる「投資」です。そのリターンを最大化するためには、単に情報を受け取るだけの姿勢では不十分です。
「What」の先にある「How」を探り、「成功事例」の裏にある「課題」に共感し、「登壇者」だけでなく「参加者」との対話を重視する。この3つの視点を持つことで、イベントは単なる情報収集の場から、自社のビジネスを前進させるための具体的なアクションに繋がる「価値創造の場」へと変わるはずです。
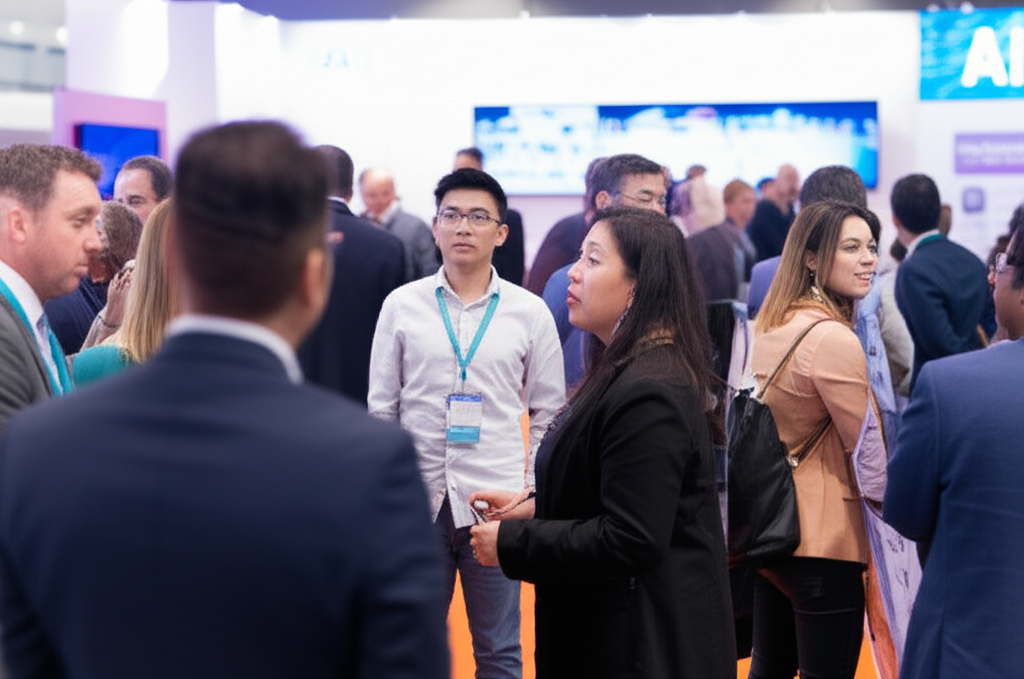

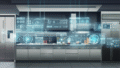
コメント