「生成AIを導入したいが、何から手をつけて良いか分からない」
生成AIの可能性に期待が高まる一方で、多くの企業がこのような悩みを抱えています。特に、専門のAI部署やエンジニアがいない非テクノロジー企業にとって、最初の一歩を踏み出すハードルは依然として高いままです。その実態は、最近の調査結果にも表れています。
2025年8月に発表された日本能率協会総合研究所の調査によると、大企業の研究開発職でさえ、情報収集に生成AIを活用しているのはわずか13.5%に留まることが明らかになりました(ZDNET Japan報道)。最先端の情報を扱うはずの研究開発部門でこの数値であることは、一般のビジネス部門における活用がさらに進んでいない可能性を示唆しています。これは、多くの企業が生成AIという強力なツールを持て余している現状を浮き彫りにしています。
なぜ、これほどまでに活用が進まないのでしょうか。その背景には、単なるツール導入だけでは解決できない、組織的な課題が存在します。
なぜAI活用は「言うは易く行うは難し」なのか
企業が生成AI活用につまずく主な理由は、複合的です。
- 人材不足とスキルギャップ: AIを使いこなせる人材が社内にいない。特に、自社の業務を理解した上で、適切なAI活用法を企画・推進できる人材は希少です。
- 具体的なユースケースの欠如: 「何ができるか」は分かっても、「自社のどの業務に、どう使えば効果が出るのか」という具体的なイメージが湧かない。
- 費用対効果への不安: 導入コストに見合う成果が出るのか確信が持てず、投資判断に踏み切れない。
- 情報過多による混乱: 毎日新しいツールやサービスが登場し、どれが自社に最適なのかを見極めるのが困難。
こうした課題は、ツールのライセンスを契約したり、数回の研修を実施したりするだけでは根本的な解決には至りません。むしろ、「公式導入25%」の裏で急増するシャドーAI:日本企業の生成AI活用、本当の課題で指摘したように、場当たり的な対応はかえって混乱を招く可能性すらあります。組織全体としてAI活用を推進するためには、体系的かつ継続的なアプローチが不可欠です。
解決策としての「伴走型支援サービス」という選択肢
こうした状況を打破する一手として、今、「伴走型」のAI活用支援サービスが注目を集めています。これは、外部の専門家が単に知識を教えるだけでなく、専任のメンターとして企業の課題整理から実務への定着までを並走してサポートするサービスです。
その代表例として、プログラミングスクールなどを手掛ける株式会社divが2025年8月に提供を開始した「テックキャンプ AI活用支援サービス」が挙げられます(株式会社divプレスリリース)。このサービスは、まさに「何から手をつけたら良いのか分からない」企業を対象に、専任メンターが伴走し、社員一人ひとりがAIで価値を生み出せるようになることを目指しています。
伴走型支援が従来のコンサルティングや研修と一線を画すのは、「教える」だけでなく「共に考え、実践し、組織に根付かせる」点にあります。具体的には、以下のような価値を提供します。
- 課題の明確化とロードマップ策定: 企業の現状や業務内容をヒアリングし、最も効果的なAI活用のユースケースを共に特定。現実的な導入計画を策定します。
- 実践を通じたスキル習得: 座学だけでなく、実際の業務データ(個人情報などをマスクしたもの)を使いながら、手を動かしてAI活用を学びます。これにより、スキルが「自分ごと」として定着しやすくなります。
- 組織的な文化醸成: 特定の担当者だけでなく、チームや部署全体で取り組むことで、生成AI活用の次なる壁:「プロンプトの属人化」を防ぐ組織的アプローチで述べたような属人化を防ぎ、組織全体のAIリテラシーを底上げします。
- 小さな成功体験の創出: まずは小さな業務改善から始め、成功体験を積み重ねることで、AI活用への心理的なハードルを下げ、全社的な展開への機運を高めます。
「教わる」から「自走する」組織へ
生成AIの導入は、ゴールではなくスタートです。真の競争力は、導入したツールをいかに自社の業務に合わせて最適化し、継続的に改善していけるかにかかっています。そのためには、外部の力に頼り続けるのではなく、最終的に組織が「自走」できる状態を目指さなくてはなりません。
伴走型支援サービスは、その「自走」に向けた最初のエンジンとなり、また自転車の補助輪のような役割を果たします。専門家のサポートを受けながら実践を重ねることで、企業は失敗を恐れずに試行錯誤でき、その過程で社内にノウハウと成功体験が蓄積されていきます。これは、「生成AI格差」に挑む新サービス:中小企業こそ外部支援を活用すべき理由の記事で触れた、特にリソースが限られる中小企業にとって、極めて有効なアプローチと言えるでしょう。
「何から始めるか」の答えは、すべての企業で同じではありません。自社の課題と向き合い、適切なパートナーと共に最初の一歩を踏み出すこと。それこそが、生成AI時代の変化を乗りこなすための最も確実な戦略なのかもしれません。

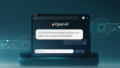

コメント