はじめに:生成AI活用の「第二章」が始まった
2025年の夏、生成AIをめぐる企業の動きは、新たなフェーズに突入したことを明確に示しています。単に「ChatGPTを試してみた」という実験的な段階は終わりを告げ、いかにして自社のビジネスプロセスに深く組み込み、具体的な成果を出すかという「実装」の段階へと移行しつつあります。この大きな潮流を象徴する動きとして、フリマアプリ大手のメルカリが打ち出した戦略が注目されています。
日本経済新聞が報じた「メルカリ、生成AIで意思決定速く 年内めどに業務系システム『統合』」というニュースは、単なる一企業のIT戦略に留まらない、業界全体の次なる課題と方向性を示唆しています。本記事では、このメルカリの「データ統合」という一手から、生成AI活用の最前線で何が起きているのか、そして企業が次に打つべき手は何かを深掘りしていきます。
なぜメルカリは「データ統合」を急ぐのか?
メルカリの発表の骨子は、経営管理、人事、経理といった、これまで個別のシステムで管理されてきた社内の業務データを年内を目処に統合するというものです。なぜ今、このタイミングでデータ統合なのでしょうか。その答えは、生成AIの能力を最大限に引き出すための「土壌づくり」にあります。
多くの企業が直面している課題は、社内のデータが部署ごと、システムごとにバラバラに管理されている「データのサイロ化」です。例えば、営業部門の顧客データはSFA(営業支援システム)に、マーケティング部門のデータはMA(マーケティングオートメーション)ツールに、経理データは会計システムに、といった具合です。
この状態では、生成AIに「全社の売上向上に繋がる施策を考えて」と問いかけても、各システムに散らばった断片的なデータしか参照できず、精度の高い分析や、部門を横断した大胆な提案は期待できません。AIがどれほど賢くても、材料となるデータが不十分であれば、その真価を発揮することはできないのです。
メルカリの狙いは、この「サイロ」を破壊し、生成AIが社内のあらゆるデータを横断的に、かつ統合された形でアクセスできる基盤を構築することにあります。これにより、これまで人間では見つけられなかったインサイト(洞察)を発見し、経営の意思決定を迅速化しようとしているのです。これは、当ブログでも以前取り上げた「AI経営参謀」の誕生を現実のものにするための、極めて重要な布石と言えるでしょう。
「データ統合」は、もはや他人事ではない
メルカリのようなテック企業だけの話だと思うかもしれませんが、この動きはあらゆる業界の企業にとって他人事ではありません。生成AIの活用が本格化するにつれて、その競争力の源泉は「どのAIモデルを使うか」から「どのようなデータをAIに与えるか」へとシフトしていきます。
この流れをいち早く察知しているのが、SnowflakeやDatabricksといったデータプラットフォーム企業です。彼らが近年、AIスタートアップの買収を積極的に進めているのは、データの重要性を誰よりも理解しているからです。詳細は過去の記事「データ企業がAIを喰らう日:Snowflake, Databricks, Scale AIの覇権戦略」でも解説しましたが、彼らは「データが集まる場所」を押さえることで、AI時代のプラットフォーム覇権を握ろうとしています。
また、国内に目を向ければ、富士通とPalantirの提携強化のように、データ分析基盤とAIソリューションをセットで提供し、企業のデータ主導型経営を支援する動きも活発化しています。これらの動きはすべて、生成AI活用の成否がデータ基盤にかかっていることを裏付けています。
まとめ:あなたの会社の「データ」はどこにありますか?
メルカリが生成AI活用の本格化に向けてデータ統合に乗り出したというニュースは、私たちに重要な問いを投げかけています。それは、「自社のデータは、今どこに、どのような状態で存在しているのか?」という問いです。
生成AIの導入を検討する際、私たちはつい最新のAIモデルや便利なツールに目を奪われがちです。しかし、その根幹を支えるデータ基盤が整備されていなければ、宝の持ち腐れになりかねません。それどころか、管理されていないデータを使って従業員が個々にAIを使い始める「シャドーAI」のリスクを高めることにも繋がります。この問題については、「公式導入25%」の裏で急増するシャドーAIの記事で詳しく解説しています。
非エンジニアであっても、自社のデータ戦略に関心を持つことが、これからの時代には不可欠です。生成AIという強力な武器を使いこなすための次なる一手は、足元にある「データ」という資源を見つめ直すことから始まるのかもしれません。

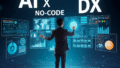
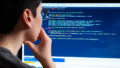
コメント