ブームの裏で突きつけられた厳しい現実
2025年、生成AIはビジネスシーンに急速に浸透し、その可能性に多くの企業が沸き立ちました。しかし、その熱狂に冷や水を浴びせるようなニュースが報じられました。日本経済新聞が報じた「生成AI、95%が利益得ず」という調査結果です。この数字は、生成AI導入を急ぐ多くの企業が、期待と現実の大きなギャップに直面していることを浮き彫りにしています。
「とりあえずChatGPTを導入してみた」「社内でハッカソンを開催した」といった取り組みは数多く聞かれますが、それが直接的な利益に結びついていないのが実情のようです。なぜ、これほどまでに期待されたテクノロジーが、ビジネスの成果に繋がらないのでしょうか。本記事では、多くの企業が陥る「PoC(概念実証)の罠」を中心に、その構造的な問題を分析し、利益創出へと舵を切るための戦略を探ります。
なぜ利益が出ないのか?多くの企業が陥る3つの構造的要因
生成AI活用が利益に繋がらない背景には、いくつかの共通した要因が存在します。特に根深いのが、PoC(概念実証)の段階で停滞してしまう問題です。
1. 目的化するPoC、「PoC貧乏」の罠
最も大きな要因は、生成AIを「使うこと」自体が目的化してしまう「PoCの罠」です。新しい技術が登場すると、まずは試してみようと考えるのは自然な流れです。しかし、そのPoCがビジネス上のどの課題を解決するのかという明確な目的設定がないまま進められるケースが後を絶ちません。
結果として、チャットボットの試作や、ドキュメント要約ツールの導入といった小規模な実証実験を繰り返すものの、そこから事業全体にインパクトを与えるような展開に繋がらない「PoC貧乏」の状態に陥ってしまいます。スモールスタートは重要ですが、その先にどのようなスケールアップ戦略を描くのか、初期段階での構想が不可欠です。
2. 見えにくい費用対効果(ROI)の壁
生成AIの導入には、ライセンス費用、API利用料、そして社員の学習コストなど、目に見えるコストが先行します。一方で、その効果は「業務が少し楽になった」「情報収集の時間が短縮された」といった定性的なものが多く、具体的な金額として算出しにくいのが実情です。
経営層は当然、投資に対するリターン(ROI)を求めます。しかし、効果測定の指標が曖昧なままでは、本格的な予算を投下する判断は下せません。短期的な成果を求めるあまり、組織全体の生産性を抜本的に変えるような、長期的視点での活用が見過ごされがちになります。
3. AIの性能を縛る「データ基盤」の未整備
生成AIの真価は、インターネット上の一般的な情報だけでなく、自社に蓄積された独自のデータを活用することで最大限に発揮されます。顧客データ、過去のプロジェクト資料、技術文書などを学習させることで、業界や自社の文脈に最適化された高精度なアウトプットが可能になります。
しかし、多くの企業ではデータが部署ごとにサイロ化(分断)されていたり、形式がバラバラでAIが学習できる状態になっていなかったりします。以前の記事「メルカリのデータ統合は号砲か?生成AI本格活用の前提条件」でも触れたように、AI活用の成否は、その前段階であるデータ基盤の整備に大きく左右されるのです。
PoCの罠を越え、利益創出へ転換するための3つの戦略
では、どうすればこの「利益の出ない」状況から脱却できるのでしょうか。ブームに踊らされることなく、着実に成果を出すための3つの戦略的アプローチを提案します。
戦略1:技術起点から「課題解決起点」への転換
まず、「生成AIで何ができるか?」という技術起点の思考から、「自社のどのビジネス課題を解決したいか?」という課題解決起点の思考へ転換することが重要です。例えば、「顧客からの問い合わせ対応に時間がかかりすぎている」「新商品のアイデア出しがマンネリ化している」といった具体的な課題をリストアップし、その解決策として生成AIが有効かを検討するのです。
このアプローチであれば、導入目的が明確になり、ROIも測定しやすくなります。中小企業の補助金申請業務のように、特定のニッチな業務に絞って活用するのも非常に有効な一手です。
戦略2:現場主導で「スモールサクセス」を積み重ねる
全社的な大規模導入を最初から目指すのではなく、まずは特定の部署やチームで小さな成功体験(スモールサクセス)を積み重ね、その効果を横展開していくアプローチが現実的です。特に、現場の担当者が自らの手で業務を改善できる環境を整えることが鍵となります。
この点で、「生成AI×ノーコード」の組み合わせは強力な武器になります。プログラミング知識のない非エンジニアでも、自部門の業務に合わせたAIツールを開発・導入できるようになり、ボトムアップでの活用が促進されます。
戦略3:自社だけで抱え込まず、外部の知見を積極的に活用する
生成AIは日進月歩の技術であり、すべての動向を自社だけで追い、最適な活用法を見つけ出すのは困難です。時には、外部の専門家の知見を借りることも重要な戦略となります。
例えば、「テックキャンプ AI活用支援サービス」のように、専門のメンターが伴走してくれるサービスも登場しています。こうした外部支援は、特に「何から手をつけて良いか分からない」という企業にとって、羅針盤の役割を果たしてくれるでしょう。当ブログでも以前、伴走型支援サービスの価値について解説しました。
「幻滅期」を乗り越え、真の活用フェーズへ
「95%が利益を得ず」という現実は、生成AIが技術のライフサイクルにおける「過度な期待のピーク期」を過ぎ、「幻滅期」に差し掛かっているサインと捉えることができます。しかし、これは決して悲観すべきことではありません。ブームが去り、熱狂が冷めた後、いよいよ地に足のついた本格的な活用の時代が始まるのです。
今、企業に求められているのは、技術先行のPoCから脱却し、ビジネス課題の解決という原点に立ち返ることです。自社のデータを整備し、現場を巻き込みながら、着実な一歩を踏み出す。それこそが、「利益の出ない95%」から抜け出し、生成AIを真の競争力へと変えるための唯一の道筋と言えるでしょう。

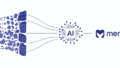

コメント