2025年現在、生成AIは私たちのビジネスやクリエイティブ活動に不可欠なツールとなりつつあります。しかし、その急速な普及とともに、生成AIが作り出したコンテンツの著作権に関する議論が活発化しています。特に、「どこまで人が関与すれば、生成AIの創作物に著作権が認められるのか」という問いは、多くの企業やクリエイターにとって喫緊の課題です。今回は、この「人の関与」の曖昧なボーダーラインに焦点を当て、生成AI時代における著作権の考え方と、企業が取るべき対策について深掘りします。
生成AIと著作権の基本原則
日本の著作権法では、「思想または感情を創作的に表現したもの」が著作物として保護の対象となります。この「創作的」であるためには、“人の思想または感情”が表現されていることが重要視されます。つまり、AI単独で生成されたコンテンツは、原則として著作権法の保護対象外と解釈されることが多いのが現状です。
しかし、生成AIを単なる道具として使い、人間が「どのようなコンテンツを作るか」「どのように表現するか」を指示し、その結果に対して修正や加筆を行う場合、その“人の寄与”が創作性を帯びる可能性があります。まさにこの「人の寄与」の度合いが、著作権が認められるかどうかの鍵を握っているのです。
「人の関与」の曖昧なボーダーライン
生成AIの創作物における「人の関与」のボーダーラインは、非常に曖昧で複雑です。例えば、以下のようなケースが考えられます。
- 単なる指示(プロンプト入力)の場合:「〇〇のテーマでブログ記事を作成して」といった一般的なプロンプト入力だけでは、AIの出力をそのまま利用した場合、人の創作性が認められにくいでしょう。
- 具体的な指示と修正・加筆の場合:「〇〇のテーマで、Aという要素とBという要素を盛り込み、Cのようなトーンで、ターゲット層Dに響くように記事を作成。さらに、出力された文章に対して、構成を大幅に変更し、表現を修正・加筆した」といった場合、人の創作性が認められる可能性が高まります。
- アイデア出しと選定の場合:AIに複数のアイデアを出させ、そこから人間が特定のアイデアを選び、さらに具体的な指示を与えて生成を進めるケース。この選定行為自体に創作性があるかどうかも議論の対象です。

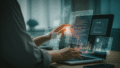

コメント