生成AIの進化は目覚ましく、2025年現在、ビジネスから日常生活まであらゆる場面でその活用が加速しています。しかし、その利便性の裏側には、誤情報の生成(ハルシネーション)や個人情報漏洩といったリスクが潜んでいることも事実です。非エンジニアのビジネスパーソンが生成AIを最大限に活用しつつ、これらのリスクを回避するための「新常識」について解説します。
東洋経済オンライン(Yahoo!ニュース配信)の記事「便利な生成AIだけど…安全に使うための注意事項。AIの嘘を見抜き、個人情報を守るために意識すべきことは?」でも指摘されているように、生成AIを安全に利用するためには、ユーザー自身が意識すべき重要なポイントがあります。
AIの「嘘(ハルシネーション)」を見抜く力
生成AIは、あたかも真実であるかのように誤った情報を生成することがあります。これを「ハルシネーション(幻覚)」と呼びます。特に、最新情報や専門性の高い内容、あるいは学習データに偏りがある場合に発生しやすい傾向にあります。非エンジニアの皆さんがこの「AIの嘘」に騙されないための実践的な対策は以下の通りです。
1. 情報源の確認と複数ソースでのファクトチェック
生成AIが提示した情報は、必ず他の信頼できる情報源(公式ウェブサイト、専門機関のレポート、大手メディアなど)で確認する習慣をつけましょう。特に重要な意思決定に影響する情報は、AIの出力を鵜呑みにせず、徹底的なファクトチェックが不可欠です。
2. 質問の仕方(プロンプト)を工夫する
具体的に、かつ明確な指示を与えることで、AIのハルシネーションリスクを低減できます。「〜について詳細を教えて」だけでなく、「〜について、信頼できる情報源を3つ挙げて、それぞれの内容を要約して」のように、情報源の提示を求めるプロンプトも有効です。当ブログの「生成AIの出力精度を極める:非エンジニア向けプロンプトエンジニアリングの最前線」でもプロンプトの重要性について解説しています。
3. RAG(Retrieval-Augmented Generation)の活用
企業で生成AIを導入する際には、RAG(Retrieval-Augmented Generation)と呼ばれる技術の採用が有効です。これは、企業内の信頼できるデータソースをAIに参照させることで、ハルシネーションを抑制し、より正確な情報を生成させる仕組みです。これにより、AIが「知らないこと」を「知っている」かのように話すリスクを大幅に減らせます。詳細については、「行政DXの要:生成AIの信頼性を高めるRAGとファインチューニング戦略」もご参照ください。
個人情報漏洩を防ぐための徹底した対策
生成AIツールに安易に個人情報や企業の機密情報を入力することは、情報漏洩のリスクに直結します。AIモデルの学習データとして利用されたり、他のユーザーへの回答に意図せず含まれたりする可能性があるためです。以下の対策を徹底しましょう。
1. 機密情報の入力は絶対に避ける
公開されている汎用的な生成AIサービス(ChatGPTなど)には、個人を特定できる情報、企業の未公開情報、顧客データ、パスワードなどの機密情報を絶対に入力してはいけません。入力されたデータがどのように扱われるか、サービス提供元のプライバシーポリシーを必ず確認しましょう。
2. セキュアな環境での利用を検討する
企業で生成AIを活用する際は、プライベートな環境で構築されたAIや、セキュリティ機能が強化された企業向けサービスを利用することが推奨されます。例えば、NTTデータが提供する「生成AI活用支援」のように、プライベートな環境で生成AIを利用できるサービスや、PaaS型AI基盤の「ABEJA Platform」などは、情報セキュリティの観点から非常に有効です。
また、AWSのようなクラウドサービスでは、生成AIアプリケーションを安全に構築するための様々なサービススタックが提供されています(AWSで生成AIアプリを構築、まずは関連するサービススタックを把握しよう)。これらの技術を活用することで、企業は生成AIの恩恵を安全に享受できます。
3. データ匿名化の徹底
やむを得ず個人情報を含むデータをAIに処理させる必要がある場合は、必ず事前に匿名化処理を施しましょう。氏名、住所、電話番号、メールアドレスなど、個人を特定できる情報を削除・置換するなどの対策が必須です。
4. 社内ガイドラインの策定と教育
企業全体で生成AIを安全に利用するためには、明確な社内ガイドラインの策定と、従業員への継続的な教育が不可欠です。ガートナーが警告する「生成AI導入の落とし穴:ガートナーが警告する「しくじり10選」」にもあるように、投資と教育は成功の鍵です。従業員一人ひとりがセキュリティ意識を高め、AIの特性を理解することが、組織全体の情報資産を守る上で極めて重要になります。
まとめ:非エンジニアが生成AIを「賢く安全に」使いこなすために
生成AIは私たちの業務効率や創造性を飛躍的に向上させる可能性を秘めていますが、その力を最大限に引き出すためには、リスクを正しく理解し、適切な対策を講じることが不可欠です。非エンジニアの皆さんも、AIが生成する情報の真偽を疑う「批判的思考力」と、機密情報を守る「セキュリティ意識」を常に持ち、賢く安全に生成AIを活用していきましょう。これにより、生成AIは単なる便利なツールではなく、あなたの強力なビジネスパートナーとなるはずです。


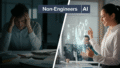
コメント