生成AIをビジネスに活用しようという機運が高まる一方、「具体的な成果に繋がらない」「アイデア出しだけで終わってしまう」といった悩みを抱える企業は少なくありません。いわゆる「PoC(概念実証)疲れ」に陥り、次のステップへ進めずにいるケースも散見されます。
こうした課題を解決する鍵は、企画と実装の間に存在する溝を埋める「実践的なスキル」にあります。アイデアを具体的な形、つまりプロトタイプにまで落とし込み、その価値を検証するサイクルを回す能力が、今まさに求められているのです。
今回は、そんな生成AI活用を「企画」で終わらせないための具体的な学びの場として、株式会社日本能率協会マネジメントセンター(JMAM)が開催する「生成AIビジネス活用実践セミナー ~企画立案からプロトタイピングまで~」に注目し、その内容を深掘りしていきます。
イベント概要
まずは、セミナーの基本情報を確認しましょう。
- イベント名: 生成AIビジネス活用実践セミナー ~企画立案からプロトタイピングまで~
- 開催日時: 2025年9月18日(木) 10:00~17:00
- 開催形式: オンライン開催
- 主催: 株式会社日本能率協会マネジメントセンター(JMAM)
- 対象者: 生成AIを活用した新規事業・サービス開発、社内業務改革の企画・推進を担当する方、DX推進部門のリーダー・担当者など
- 詳細・申込: 公式サイトはこちら
注目ポイント1:企画からプロトタイピングまでを一気通貫で学ぶ
本セミナー最大の特徴は、その名が示す通り「企画立案」から「プロトタイピング」まで、ビジネス実装に必要なプロセスを一気通貫で体験できる点にあります。
一般的な生成AIセミナーが技術の概要やユースケースの紹介に留まることが多い中、本セミナーでは具体的なビジネス課題を設定し、その解決策としてAIサービスを企画。さらに、ノーコードAI開発ツール「Dify」入門でも紹介したようなツールを活用して、実際に動作するプロトタイプを作成するまでをハンズオン形式で学びます。
アイデアを具体的な「動くモノ」にすることで、初めて見えてくる課題や改善点があります。この実践的なプロセスを経験することは、机上の空論ではない、地に足のついたAI活用を推進する上で極めて重要です。
注目ポイント2:ビジネス成果に直結する課題解決志向
JMAMは、長年にわたり多くの企業の組織開発や人材育成を支援してきた実績があります。そのノウハウは本セミナーにも活かされており、単なる技術習得ではなく、「いかにしてビジネス成果に繋げるか」という視点が貫かれています。
カリキュラムには、ビジネスモデルの検討や、導入における倫理・法務面の留意点、費用対効果の算出といった、実務で必ず直面するテーマが組み込まれています。これは、生成AI活用の実態:メリットと見過ごせない注意点で解説したような、技術導入の際に陥りがちな落とし穴を回避し、真の価値創出を目指すための羅針盤となるでしょう。
注目ポイント3:非エンジニアが体系的にスキルを習得できる設計
生成AI活用は、もはやエンジニアだけの専売特許ではありません。ビジネスサイドの人間がAIの可能性を理解し、自ら手を動かしてサービスを形にできるスキルは、今後のキャリアにおいて大きな武器となります。
本セミナーは、まさにそうした非エンジニアのビジネスパーソンを対象に設計されています。プログラミングの知識がなくても、生成AIの仕組みから、効果的なプロンプトの設計、そしてノーコードツールを使ったアプリケーション開発まで、必要な知識とスキルを体系的に学ぶことができます。これは、当ブログでも警鐘を鳴らしてきた生成AI時代の「スキル格差」を埋め、組織全体のAIリテラシーを向上させる絶好の機会と言えるでしょう。
まとめ
生成AIのビジネス活用は、新たなフェーズに突入しています。単に「知っている」「使ってみた」というレベルから一歩踏み出し、自社の課題解決のために「創り出す」ことが求められています。
今回ご紹介したJMAMの「生成AIビジネス活用実践セミナー」は、そのために必要なスキル、知識、そしてマインドセットを1日で集中的に獲得できる貴重な機会です。アイデアを形にし、ビジネスを前進させるための具体的な一歩を踏み出したい方は、ぜひ参加を検討してみてはいかがでしょうか。
詳細・申込はこちらから:
https://www.jmam.co.jp/hrm/seminar/category/dx/t153.html

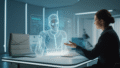
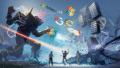
コメント